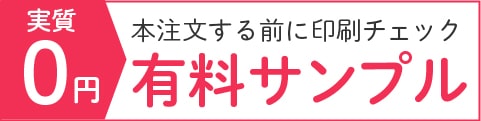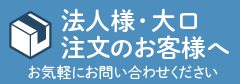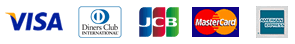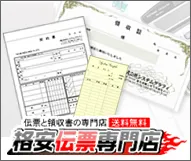使用できる書体(フォント)の種類
書体の種類としては、基本書体のほかに毛筆体、POP体などがあり、それぞれの種類の中にも細かく分類が分かれた書体が発生します。
また、一つの書体でも影付け、重ねなどの飾りが付いたり、線の太さ(ウエイト)によって何種類にも分かれていたりします。
下のフォントを参考に注文してください。
また、一つの書体でも影付け、重ねなどの飾りが付いたり、線の太さ(ウエイト)によって何種類にも分かれていたりします。
下のフォントを参考に注文してください。
明朝体

横線が細く、縦線が太い。書籍などの本文用活字として最も普通に使われている。
ゴシック体(セリフ系)
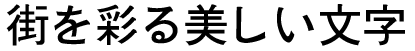
全体に同じ太さの線でできており、角ばっている書体。 また、米国ではゴシックあるいはブロック‐レター、英国ではサン‐セリフ、欧州ではグロテスクと呼ぶ。欧米ではゴシックはブラック‐レターのことをさす。
ゴシック体(サンセリフ系)
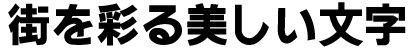
セリフのないゴシック体。「サン」とは無いという意味。欧文のゴシック体は普通サンセリフ。
丸ゴシック体

ゴシック体の角などにラウンド処理を施した柔らかみのある書体。
教科書体
教科書で用いられる楷書的書体。書き順やハネやトメ、画数がハッキリしているのが特徴。
楷書体
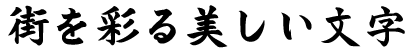
隷書から転化したもので、点画をくずさない書き方。魏(三国)の鍾ようがこれを改良し大いに流行。真書。正書。真。楷。
隷書体
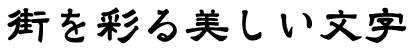
秦の雲陽の程ばくが篆書を簡単にした直線的な字体を、漢代に装飾的に変化させた書体。後世、これを漢隷または八分といって古い隷書と区別したが、一般に隷書といえば漢隷を指す。楷書を隷書ということもある。漢代の書記や庶務係(下級役人)がメモに用いた。
古印体

奈良時代から平安時代末期まで、日本で作られ使用された印章。隋・唐の様式にならった鋳銅印で、公文書などに押された。和様化した篆書や楷書が多く、すべて朱文。
篆書
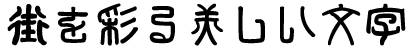
大篆・小篆があり,隷書・楷書のもとになった。現在は、印章などに使われる。篆文。
勘亭流
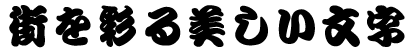
歌舞伎の看板または番付などを書くのに用いる書風。肉太で丸みを帯びる。江戸中村座の手代岡崎屋勘六(号、勘亭)から始まるという。
江戸文字
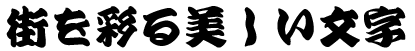
江戸で、興行の看板や番付に用いた独特の書体の文字の総称。歌舞伎の勘亭流のほか、寄席文字・相撲文字など。
POP体
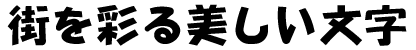
店頭広告.屋外看板、ショー‐ウインドー、店内ポスターの類などに用いられる、太く軽快さを持った書体。パソコンのPOP書体には細い文字も存在する。
他にも、英数字や記号の表示に使用することができるフォントもあります。
| Arial |  |
|---|---|
| Arial Rounded MT |
 |
| Arial Black Italic |
 |
| Broadway |  |
| Century |  |
| CASTELLAR |  |
| Elephant |  |
| Franklin Gothic |  |
| Impact |  |
| Lucida Calligraphy |
 |
| Old English Text |
 |
| Rocwell |  |
| Kunstler Script |
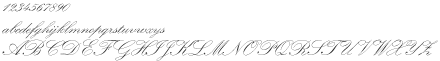 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
■:休業日
休業日にはメールの返信・電話でのお問い合わせ・ご注文の確認や変更などができませんのでご了承ください。
ご返信は営業日中1〜2日以内にご連絡いたします。
ご返信は営業日中1〜2日以内にご連絡いたします。